子亀の脱走
 生後約4カ月の子亀(甲長46㎜)を屋内水槽(トロ舟)で飼い始めて6日目に、カバー(上蓋)として利用していた百均ワイヤーネットの網目を潜り抜けて脱走した。
幸い部屋の中で直ぐに見つかったので無事だったが、まさか網目を潜り抜けられるとは全く考えていなかったので驚いた。
ワイヤーネットをもう一枚重ね、縦横に半格子ずらした位置で結束バンドで固定した。
生後約4カ月の子亀(甲長46㎜)を屋内水槽(トロ舟)で飼い始めて6日目に、カバー(上蓋)として利用していた百均ワイヤーネットの網目を潜り抜けて脱走した。
幸い部屋の中で直ぐに見つかったので無事だったが、まさか網目を潜り抜けられるとは全く考えていなかったので驚いた。
ワイヤーネットをもう一枚重ね、縦横に半格子ずらした位置で結束バンドで固定した。
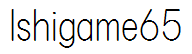
 生後約4カ月の子亀(甲長46㎜)を屋内水槽(トロ舟)で飼い始めて6日目に、カバー(上蓋)として利用していた百均ワイヤーネットの網目を潜り抜けて脱走した。
幸い部屋の中で直ぐに見つかったので無事だったが、まさか網目を潜り抜けられるとは全く考えていなかったので驚いた。
ワイヤーネットをもう一枚重ね、縦横に半格子ずらした位置で結束バンドで固定した。
生後約4カ月の子亀(甲長46㎜)を屋内水槽(トロ舟)で飼い始めて6日目に、カバー(上蓋)として利用していた百均ワイヤーネットの網目を潜り抜けて脱走した。
幸い部屋の中で直ぐに見つかったので無事だったが、まさか網目を潜り抜けられるとは全く考えていなかったので驚いた。
ワイヤーネットをもう一枚重ね、縦横に半格子ずらした位置で結束バンドで固定した。

 前回のアライグマに再びケージ内に侵入されてしまった。
今回はケージ上部開口部のドアを(まさか手で?)静かに持ち上げて入ってきて、
池の水を飲んでから再びドアを押し上げて出て行ったようだ。
ドアを重みでこじ開けられない仕組みだけでは不十分と分かったので、
新たにプラスチックチェーン用のねじ込み式ジョイントを取り付けた。
前回のアライグマに再びケージ内に侵入されてしまった。
今回はケージ上部開口部のドアを(まさか手で?)静かに持ち上げて入ってきて、
池の水を飲んでから再びドアを押し上げて出て行ったようだ。
ドアを重みでこじ開けられない仕組みだけでは不十分と分かったので、
新たにプラスチックチェーン用のねじ込み式ジョイントを取り付けた。
 気づいたら自動給餌器の電池が腐食して給餌しなくなっていた。
雨に濡れないようにカバーを取り付けているが、
屋内使用前提の給餌器を高温多湿の屋外環境で使用することに無理があるのだろう。
録画映像を確認したところ3日前まで正常に動作していたようだ。
亀たちは元気で、新しい電池に入れ替えたら正常に動作したので良かったが、
定期的な確認は欠かさないようにしよう。
気づいたら自動給餌器の電池が腐食して給餌しなくなっていた。
雨に濡れないようにカバーを取り付けているが、
屋内使用前提の給餌器を高温多湿の屋外環境で使用することに無理があるのだろう。
録画映像を確認したところ3日前まで正常に動作していたようだ。
亀たちは元気で、新しい電池に入れ替えたら正常に動作したので良かったが、
定期的な確認は欠かさないようにしよう。